青山二郎⑥青山学院の「揉み揉まれ」 [読書・言葉備忘録]
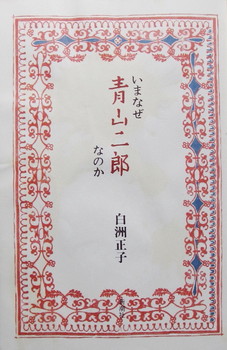 青山学院の教育法は、酒席での「(議論)揉み合い」。青山は骨董の真贋を見分ける要領(生半可な先入観・固定観念なく、無私無欲の肉眼観賞で感じる・見るが肝心)で、文学者らの「人間の真贋」を見抜き、相手を泣かすほど、蛇が蛙を呑み込むほどにコテンパンに打ちのめすそうな(それでも一カ所は逃げ場を残しておくのが規則だったとか)。
青山学院の教育法は、酒席での「(議論)揉み合い」。青山は骨董の真贋を見分ける要領(生半可な先入観・固定観念なく、無私無欲の肉眼観賞で感じる・見るが肝心)で、文学者らの「人間の真贋」を見抜き、相手を泣かすほど、蛇が蛙を呑み込むほどにコテンパンに打ちのめすそうな(それでも一カ所は逃げ場を残しておくのが規則だったとか)。 靑山の最後の弟子・白洲正子の場合。彼女が差し出した原稿に、青山は朱を入れるどころか目の前でズタズタに引き裂き「説明は不必要で冗漫。形容詞が多過ぎる」。さらには「ここがあんたの一番いいたいところだろ」とそれも不用とした。「自分が言いたいことを我慢すれば、読者は我慢した分だけわかってくれる。そこが読者の愉しみなのだから」。白洲は「へどを吐く」ほどにやっつけられながら、それでも通ったそうな。
小林秀雄の場合。小林は3年間の骨董修業を通じて「やっと文学がわかるようになった」と述懐したそうな。骨董には人間の愛着や欲念の歴史が積もっていて、一種の魔力を秘め持つようになる。それは実際に骨董を手に入れなければ無きに等しい日用品。自分の物にして使い込み愉しむようになって、初めて良さがわかる。茶道とは器を観賞し、実際に使って、その器の美しさを知る道。そうして過去を現在に甦させる=歴史の魂に触れる。つまり過去の文化遺産を現代に甦らせてこそ伝統になる。
 小林はかくして「言葉」をもって過去の文化遺産(伝統)を現代に甦らせるべく『徒然草』(兼好法師)を書いた。「徒然なるまま」に書きつつも「眼が冴えて、物が見え過ぎ、物が解り過ぎて」〝怪しうこそ物狂ほしけれ〟に至る心が解るとした。
小林はかくして「言葉」をもって過去の文化遺産(伝統)を現代に甦らせるべく『徒然草』(兼好法師)を書いた。「徒然なるまま」に書きつつも「眼が冴えて、物が見え過ぎ、物が解り過ぎて」〝怪しうこそ物狂ほしけれ〟に至る心が解るとした。 美しい花を見る。例えばそれが「菫」と解ると同時に、眼は閉じて頭(言葉)で見るようになってしまう。言葉が邪魔をする。小林は骨董の修行を通して、言葉が邪魔をするスキを与えず、初めて「見えて来る」ようになったと自己分析をする。物が解りだして、彼は『無常という事』『平家物語』『西行』などの過去の遺産を次々に現代に甦らせた。
青山もその眼で『利休』を書き、『梅原龍三郎』『富岡鉄斎』を書いた。かくして〝青山学院〟の小林秀雄を筆頭に河上徹太郎、中原中也、中村光夫、大岡昇平、白洲正子らに「青山が私を築いた」と言わしめ、また彼らが実際に活躍する姿を見て、我も我もと弟子入り絶えず~とか。
加えて青山は仲間作家の装幀も手掛けた。これがめっぽう魅力的でインパクトもあった。小生は青山学院の作家らを読んだことがないゆえ、以上の記述を読んでも、納得し難いのが実情。まぁいずれは読む時が来るかもです。
だがそんな子弟関係に亀裂も走る。小林秀雄は昭和28年(1953)に欧米旅行から帰国すると、有名なセリフ「過去はもう沢山だ」を吐き、青山二郎と決別した。理由は諸々だが、その中のひとつが、青山学院の青年らを吉原に連れ行きて「男」にするも、全員が淋病に罹ったことも恨んでいたとか。写真は白洲正子著『いまなぜ青山二郎か』の扉とグラビア。
2021-04-21 07:38
nice!(0)
コメント(0)




コメント 0